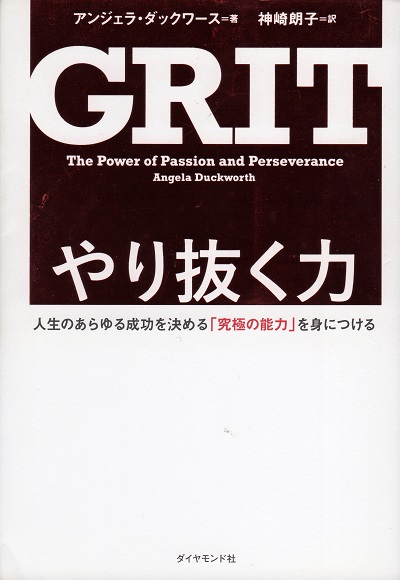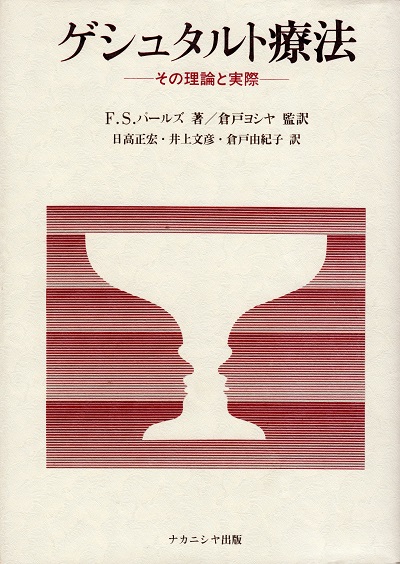ブログ 岡本浩和の「人間力」発見日記
-

2.212025
道は付きもせず、また離れもせず
昨夜の学び。情に掉させば流される。とは夏目漱石の「草枕」の冒頭の一節です。同情すれば、負のエネルギーさえも引っ掛けてしまいます。人に何かをして差し上げるとき、何も要求しない形でないとその人の業までを背負ってしまうということです。
続きを読む -

2.202025
君君、臣臣、父父、子子
15年位前に買ったスーツを久しぶりに着たら、腰回りと胴回りがきつくなっておりました。最近よく食べるから、ひょっとしたらこれまでの人生にないくらいの体重になっているかと思い、今朝、体重計に乗りました。61.6kg。これまでの記録は62kgくらいでしたから、人生でほぼ一番肥っているということです。
続きを読む -

2.192025
生命の根源は呼吸と鼓動
昨夜は、仲間たちと三鷹市芸術文化センターに集合しました。風のホールで開かれた東京藝術大学打楽器専攻生有志によるPERCUSSION ENSEMBLEの演奏を聴くためでした。
続きを読む -

-

2.172025
すべては心の持ち様、僕たちはそもそも前向きな存在です
昨夜は、「3つのお宝」のお話を聞く会の後、残った方たちと食事を共にしました。僕は20時からオンラインでのミーティングがあったので途中で抜けましたが、結局22時近くまで歓談が続いたようです。
続きを読む -

2.162025
「求める心」こそが問題の根源です
今日は朝早くから部屋の掃除に勤しみました。天気も良く、気温も高く、暖房なしで一日過ごしました。午後、昨年からスタートした「3つのお宝」のお話を聞く会。古い方から最近の方まで老若男女(?)集まっていただいての濃密な会。
続きを読む -

2.152025
躊躇は禁物、思ったが吉日
妻の伯母さん(義父の実姉)が12日に亡くなったと聞きました。2020年2月の披露パーティーでお会いし、その後、2022年の11月に自宅を訪問して以来僕は会っていませんでした。
続きを読む -

2.142025
すべてを上手に活かせるかどうか
昨日は、研修の動画撮影日でした。5本目になるので要領がつかめ、すべてがスムーズに運びました。僕たちは、つくづく関係あっての存在であることを思います。動画撮影では、聴き手は不在。自ら相手を想像しながら話を進めていくのですが、目の前に相手がいるのとそうでないのとでは基本的に熱量が違ってきます。
続きを読む -

2.132025
世界はバランスの中にあります
この世界で上手に生きていくのに、バランスはとても大切です。人間の基本能力には、能動能力と受動力があり、その2つを足して100になるようにインストールされているとも言われます。
続きを読む -

2.122025
ありがたや、ありがたや
東京に戻りました。わずか4日間でしたが、父母と水入らずの良い時間を過ごすことができました。最寄りの駅を下りたら大抵、無事着いたことを電話で報告します。昨日は「お婆がおーきにやったと言うてるわ」と父が言いました。
続きを読む